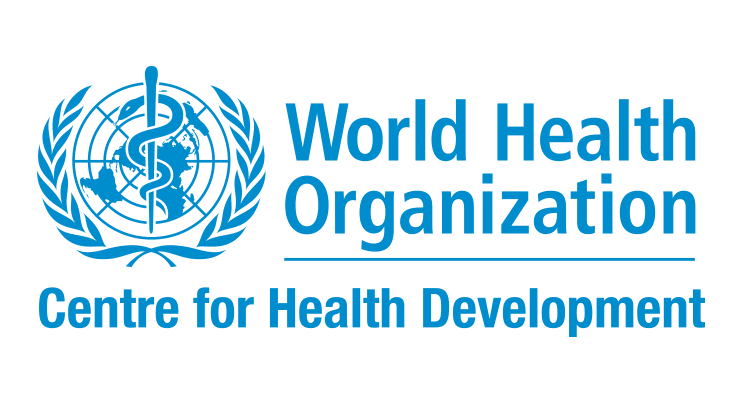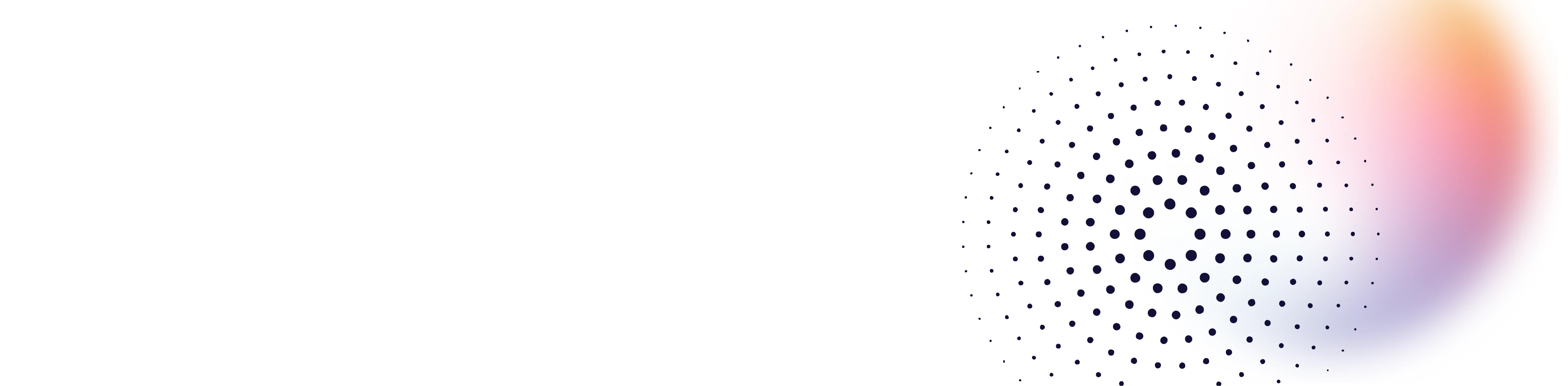WKCフォーラム「高齢者のためのイノベーション ~アドヒアランス向上のために: 薬剤治療と食事療法~ 」

10月1日は、国連の定める 国際高齢者デー(International Day of Older Persons)です。この日を記念して、WHO神戸センター(WKC)は、2014年10月1日(水) 神戸にて、公開フォーラム「高齢者のためのイノベーション ~アドヒアランス向上のために: 薬剤治療と食事療法~」を開催します。
人口に占める高齢者の割合は、世界的に急激な増加の一途をたどっています。現在、ほとんどの国で、最も急速な増加がみられる人口区分は80歳以上の高齢者層です。今後40年のうちに、高齢者人口は現状のほぼ3倍に拡大すると予測されており、この現象の大部分は開発途上国に集中するとみられています。このような人口転換に伴って疾病構造の変化(疫学的転換)もみとめられています。世界的にみて、非感染性疾患が主な死亡原因となり、また、非感染性疾患に起因する障害の割合は障害全体の50%にも上っています。この傾向がきわめて顕著な日本は、世界で最も高齢化の進んだ国であると同時に、非感染性疾患が死亡原因の80%近くを占める現状を抱えています。
従来、医療における患者の療養行動は、「医療者からの指示に患者がどの程度忠実に従うか」というコンプライアンス概念のもと、受身の立場で評価されてきました。しかし、治療の過程では、服薬、食生活の改善、生活習慣の修正など、患者と医療者が相互に合意した治療方針に患者自身が主体的に参加する必要性が重視されるようになってきました。この概念をアドヒアランスと呼びます。
加齢に伴う健康課題の多くについては予防や管理が可能です。そのためには、老化による認知や機能の低下、また、健康や生活の質の維持を目的とした療法にいくつも取り組まなければならないなど、高齢者が日々直面する問題にうまく対処することが肝要です。アドヒアランスは、治療を成功に導く第一の決定要因です。アドヒアランスが不十分であれば、治療効果を最大限に引き出すことは難しく、ひいては、医療制度における全般的な有効性を引き下げることにもつながります。
加齢とともに、栄養必要量は変化していきます。同時に、健康問題や複数の薬剤服用による副作用、生活様式の変化、知識不足などが原因で、必要な栄養摂取が損なわれることも考えられます。食習慣や服薬におけるアドヒアランスは、健康な高齢化のための大切なポイントとして、健康状態の改善に深く結びつています。
今回のフォーラムでは、老年学、薬学、栄養学の分野から4 名の専門家を迎え、高齢者の健康に寄与するアドヒアランス向上についての講演、ならびに、参加者からの質疑に応じる形式での活発な討議を展開します。
開催日時・場所:
2014年10月1日(水)14:00~16:00
WHO神戸センター
プログラム:
(言語:日本語)
14:00~14:05 開会の辞
14:05~15:20 講演
15:20~15:55 討議(オープンディスカッション)
15:55~16:00 閉会の辞
講演者: (登壇順・敬称略)

「服薬と栄養についてのアドヒアランス: 健康で幸せな高齢期のために」
神戸大学 小田利勝 名誉教授
北海道大学文学部、同大学院文学研究科で社会学を専攻。北海道大学助手、徳島大学助教授、教授を経て1996 年神戸大学教授、2007 年神戸大学大学院教授、2013 年3 月定年退職。学術博士(1987 年、北海道大学)。保健医療行動や病気を抱えた家族の生活過程、地域の保健医療システム、個人や組織の国内外での災害対応行動、マレーシアの農村開発、高齢者問題や少子・高齢化問題など、人間と社会をめぐる種々の問題に関して社会学や社会心理学、地域計画学の観点から幅広く研究してきた。近年では、主にサクセスフル・エイジングの研究を進めており、現在は、少子高齢・人口減少社会におけるサクセスフル・エイジングの実現には老年学的想像力の発揮が必要であるという認識に基づいて研究を進めている。
『かつて高齢者は、「役割なき役割」の中に閉じ込められていて、果たすべき重要な役割を持たない、と言われたことがあります。しかし、少子・高齢化が進行する日本において、今日およびこれからの高齢者には多大な役割を果たすことが期待されています。それらの役割の中には、労働力として、また消費人口として経済を支える役割や一大勢力を形成するようになった有権者として政治に果たす役割、そして、何よりもできる限り長期にわたって自立生活が可能なように健康を維持する役割が期待されています。栄養摂取や服薬は、そのための基本的手段ですが、服薬が必要になったときには、病人に期待される役割が生じます。アドヒアランスとは、社会学的に言えば、期待される病人の役割を遂行することです。講演では、幸せな高齢期の生活すなわちサクセスフル・エイジングの実現へ向けたアドヒアランスや栄養摂取について、社会学や老年学の理論から話題を提供します。』

「高齢者の服薬をモニタリングする新たなツール: 日本における臨床研究」
横浜薬科大学 臨床薬学科 薬理学研究室 定本清美 教授
東邦大学医学部卒。リウマチ学を専攻、医学博士(東邦大学)。専門は、内科リウマチ・膠原病学、臨床薬学。東邦大学、東海大学にて臨床リウマチ学を研究。英国・バーミンガム大学では社会科学修士を取得、リサーチフェローとして関節リウマチの臨床にも従事。英国より帰国の後、東邦大学医学部にて病院管理にも携わる。薬学分野では、東邦大学での研究・教育活動の後、2013年より横浜薬科大学にて現職。東邦大学在籍時に着手した患者の服薬を容易にするためのユニバーサルデザイン包装などの臨床薬学における研究は、関節リウマチ患者や障害者、高齢者の負担軽減にも関連づけた成果が期待されている。
『医療においては様々な治療が施行されますが、薬物治療はどんな場合でも根幹となる重要なものです。薬物治療を受ける機会が多い高齢者にとって、薬を正しくまた無駄なく服用することは、個人の治療効果の向上に必要なばかりでなく、医療経済的な意味においても重要であるといえます。共同開発した服薬をモニタリングするツールを用いて、服薬についての臨床研究を行った背景や結果、今後の展開の可能性などについて述べたいと思います。』

「日本人高齢者の栄養と健康維持」
名古屋学芸大学大学院 栄養科学研究科 下方浩史 教授
1977年名古屋大学医学部卒。1982年名古屋大学大学院博士課程満了(第3内科)。名古屋大学医学部老年科に医員として入局。1986年~1990年米国国立老化研究所(NIA)へ客員研究員として留学。1990年広島大学助教授、1996年国立長寿医療センター研究所疫学研究部長、2010年予防開発部長を経て、2013年より現職。2014年からは名古屋学芸大学健康・栄養研究所所長を兼務。厚生労働省の長寿科学総合研究、認知症対策総合研究などの主任研究者として長寿、老化に関する疫学的研究を行っており、栄養や運動などの生活習慣が老化や老年病に及ぼす影響を解明して、健康長寿を達成するための方法論の確立を目指している。
『健康長寿を目指すには食生活の改善が有用です。現代社会ではメタボリックシンドロームと老年病が大きな問題になっています。肥満は多くの疾病の原因ではありますが、75歳以上の後期高齢者ではむしろ栄養不足への対策が重要です。栄養は高齢者の健康維持の鍵となっています。しかし、食生活と疾病との関係には個人差が強く現れます。今後は個人差に注目した疾病予防が重要な時代となるでしょう。』

「高齢期に適切な食事摂取とは」
京都大学東南アジア研究所 日本学術振興会特別研究員 木村友美
2007年奈良女子大学食物栄養学科卒。2009年京都大学医学研究科社会健康医学系専攻専門職学位過程修了、2012年同専攻博士課程修了、博士号(社会健康医学)取得。2011年より、WHO神戸センターの研究プロジェクトに参加し、「都市化と健康」に関するデータベースの構築、日本の介護予防事業や健康寿命についての研究に携わった。2014年より、日本学術振興会の特別研究員として京都大学東南アジア研究所に勤務。地域に暮らす高齢者の健康状態や食事摂取状況を包括的にとらえる「フィールド医学」調査を行っている。高齢者の健康と食に関する科学的エビデンスを蓄積し、「食からの介護予防」を目指している。
『「バラエティ豊かな食事を」とは、厚生労働省の提示する食事指針にも記されている標語ですが、多様な食品の摂取が健康長寿に寄与することは、実際に世界の様々な研究で報告されています。しかしながら、加齢とともに、食の多様性は乏しくなると言われており、その要因は、加齢に伴う運動量の低下、消化機能や咀嚼能力の低下など、複合的で多岐にわたります。また、高齢になると、様々な慢性疾患を複数かかえているという人が珍しくないため、そのような疾患に配慮した食事摂取も必要になってきます。食は単に栄養素の摂取だけでなく、日常のなかでの楽しみや人との交流に関わる重要な側面をもち、心理的な健康度に関与します。高齢者の虚弱を防ぎ、心身ともに健康な状態を維持するための食事摂取について、これまでのフィールド調査や世界の研究報告から考察します。』
詳しくはこちら:フォーラム開催のご案内・参加申し込み方法
参加費無料
事前申し込み締め切り:
2014年9月26日 (金)