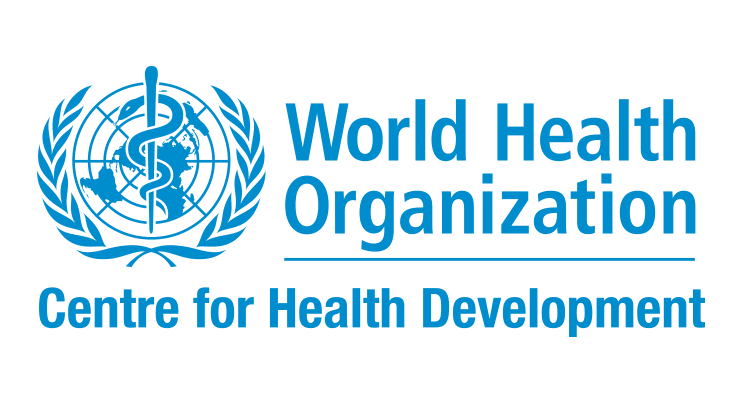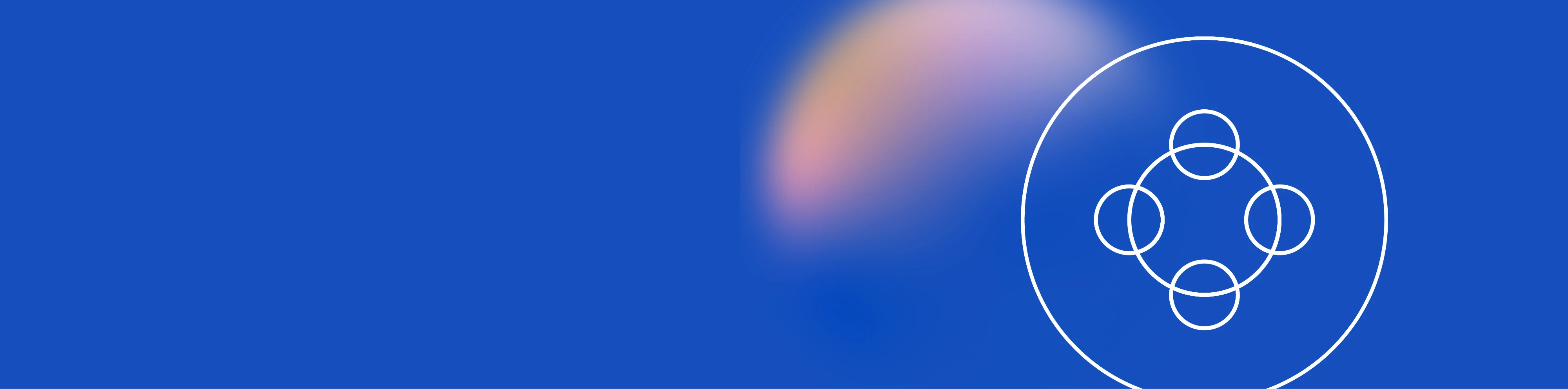Local engagement
The WHO Kobe Centre (WKC) was established in 1995 with strong financial and material support and collaboration from the Kobe Group through a decision of the World Health Organization Executive Board. The Kobe Group includes Hyogo Prefecture, Kobe City, the Kobe Chamber of Commerce and Kobe Steel. Given that it functions as a department of WHO Headquarters but was also established as a result of strong local support, the WKC has both a global and a local mandate. The focus of WKC local engagement is three-fold.
What is our focus?
- To share lessons learned across countries and encourage global collaboration as countries strive to attain their commitments under the Sustainable Development Goals (SDGs).
Lessons learned from the Kansai community are integrated into our research efforts. As a result, we have established collaborative research programmes with Kansai-based research institutions as an integral part of our research programme. We also hold international meetings and support the WHO Health Emergency and Disaster Risk Management Research Network.
- To communicate and disseminate information about WKC’s research activities in the local community.
To strengthen communication and dissemination of WKC research findings and results, the WKC organizes at least three WKC fora every year in close cooperation with the Kobe Group. We use Twitter and YouTube to disseminate information about WKC research to the community, and have translated the website into the Japanese language. We also work with local media to inform the community about what we do.
- To contribute to the community in Kobe and Hyogo prefecture for health awareness-raising and health advocacy.
As part of our contributions to Kobe and Hyogo prefecture in the health field, the WKC staff participate in many technical committees ranging from emergencies to infectious and non-communicable diseases. We also translated WHO disease outbreak reports (DONs) for dissemination; in 2020, we focused on translation of WHO COVID-19 technical guidances and COVID-19 public information. Please see our COVID webpage here. We also conduct lectures about WHO and WKC work in primary and secondary schools in the Kansai region, and universities. Contact us to request a presentation!
Why is this important?
The WKC staff strive to be a part of and contribute to a thriving healthy local community.
Read more about our latest activities.
新しいウェブサイトに移行しました!
WHO健康開発総合研究センター(WHO神戸センター)は、2023年11月をもって新しいウェブサイトに移行しました。https://wkc.who.int/
こちらのウェブサイト(https://extranet.who.int/kobe_centre/ja)は今後更新されませんが、現在掲載されているコンテンツは2023年12月中旬まで閲覧可能です。
操作性が向上し新たな機能が追加された新ウェブサイトで、新たなコンテンツや情報をぜひご覧ください!

2023年ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ・デーに寄せて WHO神戸センター所長のメッセージ
12月12日はユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)デーです。WHO健康開発総合研究センター(WHO神戸センター)は、2023年9月21日にニューヨークで採択されたUHC政治宣言を受けて、世界各国がUHC達成に向けて決意を新たにしたことを心強く思います。
今年のテーマは「すべての人に健康を:今こそ行動を起こす時」。当センターは、持続可能な開発目標(SDGs)のすべての目標の達成において、UHCが要となると考えています。
UHCの進捗を測るためには、保健医療サービスのカバレッジと経済的保護という重要な2つの指標があります。特に高齢者のケアにおける満たされないニーズ(アンメットニーズ)に関するWHO神戸センターの研究は、WHOと世界銀行による「UHCグローバル・モニタリング・レポート2023」や、2023年9月に開催された国連総会ハイレベル会合での議論に活用されました。
UHCに向けた資金確保は、コストではなく投資です。例えば慢性疾患を抱える人に対するケアの質の向上は、予防可能な死亡の減少につながり、UHCを推進する上でも重要です。急速な人口高齢化を考慮すると、慢性期ケアの質の向上に対してインセンティブが与えられるように、ケアサービス提供者への支払い体系などを改正していく必要があります。
当センターはWHOの主要プロジェクトとして、WHO本部やOECDの研究者とともに「慢性疾患に対する質の高い保健医療サービスを強化するための購入手段」に関する研究を実施しました。この研究では、ケアサービス提供者に対する異なる種類の支払い方式が、慢性期ケアの質を向上させるインセンティブになるかどうかを調査しました。
支払い方法の効果に関する厳密な評価はまだ不十分ですが、8か国での事例調査(※1)では、医療情報システムとテクノロジー、強力なリーダーシップ、マルチステークホルダーの関与が、慢性期ケアの質の向上を促す要素であることが明らかになりました。このようなエビデンスは、保健医療サービスの提供モデル全体や、保健医療への支払い方法によってサービスの質の向上を図れる点について、より一層焦点をあてるべきであることを示しています。
今年のUHCデーに際し、2030年のUHC達成に向けて世界が前進しすべての人が健康を享受するためにも、各国のリーダーたちが保健医療に対してより賢明に投資するよう、世界中の人びととともに要請します。UHCへの投資不足は、計り知れないほど多くの損失につながるでしょう。
※1 質の高い慢性期ケアに向けた報酬設定に関する当センターの研究については、オーストラリア、カナダ、チリ、中国、ドイツ、インドネシア、南アフリカ、スペインの事例調査をご覧ください。

災害・健康危機管理に関する国際専門家会議が神戸で開催
2023年11月13日と14日に、第 4 回WHO「災害リスク管理とレジリエンス構築」部門担当官年次会議とWHO神戸センターが主催する、第5回WHO災害・健康危機管理に関するグローバルリサーチネットワーク代表者(コアグループ)会議が神戸で開催されました。
11月13日に開催されたWHO「災害リスク管理とレジリエンス構築」部門担当官年次会議では、WHO本部、全WHO 地域事務局の担当官、WHO神戸センターが2023年の成果、課題を共有し、2024年に向けての優先事項を決定しました。
11月14日午前の部で、WHO災害・健康危機管理に関するグローバルリサーチネットワークの代表者(コアグループ)会議が、事務局を務めるWHO神戸センターにて開催されました。こちらの会議には、世界的な研究者である2人の共同議長、Professor Virginia Murray とAssociate Professor Jonathan Abrahamsをはじめ、WHO本部、WHO 地域事務局の「災害リスク管理とレジリエンス構築」部門担当官、事務局を務めるWHO神戸センターと外部の主要な災害・健康危機管理分野の専門家が参加しました。本会議では、Health EDRM RNの2024年に向けた災害・健康危機管理に関する研究の普及方法と効果的実践計画案が検討されました。WHO神戸センターは、WHO本部、そして各地域事務局と連携し、国際的なステークホルダーも取り込んでグローバルな研究活動と、政策や現場での実践をつなげるための手法や資源調達に関しての具体的な方策(webinarやワークショップ)を推進していきます。

神戸市における新型コロナウイルス感染症流行期の行動変容とその健康への影響に関する共同プロジェクトを開始
WHO神戸センターは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行がもたらした健康二次被害に関する調査研究プロジェクトを、神戸市の協力のもと、日本老年学的評価研究機構(JAGES)と共同で実施します。パンデミックの初期段階では、多くの人々が感染への恐怖や移動制限、経済的困難などの理由から、必要な医療を受けることができませんでした。 日本では、身体活動や社会活動の減少などによって高齢者の健康状態が悪化するリスクが高まった可能性が研究で示されています。一方で、そうしたCOVID-19の流行により引き起こされた行動変容が健康に与えた影響についての調査研究は、世界的にも日本国内においても不十分です。
このプロジェクトでは、神戸市の市民約40万人が登録されている「ヘルスケアデータ連携システム」と、神戸市で2018年に実施された「市民の健康とくらしの調査」に加えて、「市民の健康とくらしの調査」を2023年に新たに実施し、これらすべてのデータを研究に活用します。
本研究の結果は、神戸市の保健事業や市民の健康リスク低減に向けた施策に資することが期待されます。また、国内外の他の地域にも有用な情報を提供することを目指します。
本プロジェクトの詳細についてはこちらをご参照ください。
当センターのプレスリリースはこちら
JAGESのプレスリリースはこちら
神戸市による記者発表資料はこちら
Photo credit: WHO / Until Chan

WKCフォーラム2023「Build the world we want; A healthy future for all」の開催報告
学生が主体となってグローバルヘルスの課題について学び議論するWKCフォーラム「Build the world we want; A healthy future for all 地球的視野に立ち、健康をとらえる」が、 inochi WAKAZO project との共催で10月1日に開催されました。対面とオンラインのハイブリッド開催となった今回、日本全国から約100名の学生および一般の参加者が参加しました。基調講演では、慶応義塾大学医学部 医療政策・管理学教室の野村周平准教授より「Health beyond borders」を主題に、国際的な視野から健康格差や医療・パブリックヘルスをめぐる世界の現状について講演いただきました。また、視聴者参加型のグループディスカッションでは、今回のフォーラムに先立ち開催された「WKCサマースクール」の参加者およびinochi WAKAZO projectの学生たちが主導するかたちで、「地球環境と健康」「紛争と健康」など健康に関する10のテーマについて活発な議論がなされました。続いて行われたパネルディスカッションでは、基調講演に登壇された野村准教授をはじめ、大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室 川崎良教授、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 近藤尚己主任教授にご参加いただき、代表の学生2名と「私たちで未来の健康を創造しよう」をテーマに様々な意見交換がなされました。フォーラムの運営大学生により作成された提言書には、10のテーマに対する学生の研究結果と意見が記され、手交式にて WHO神戸センター所長サラ・ルイーズ・バーバーと兵庫県保健医療部 山下輝夫部長にお受け取りいただきました。