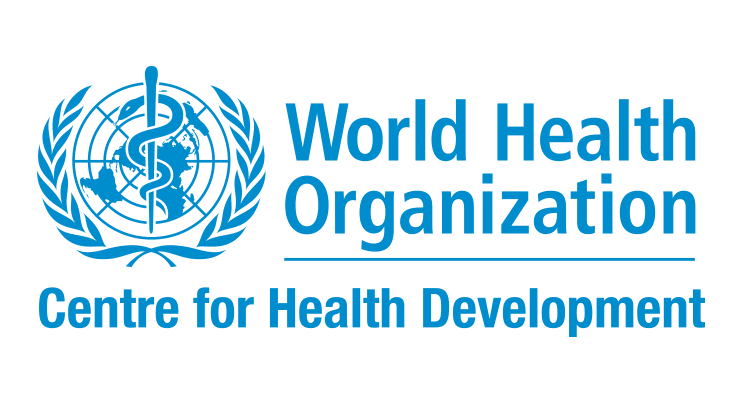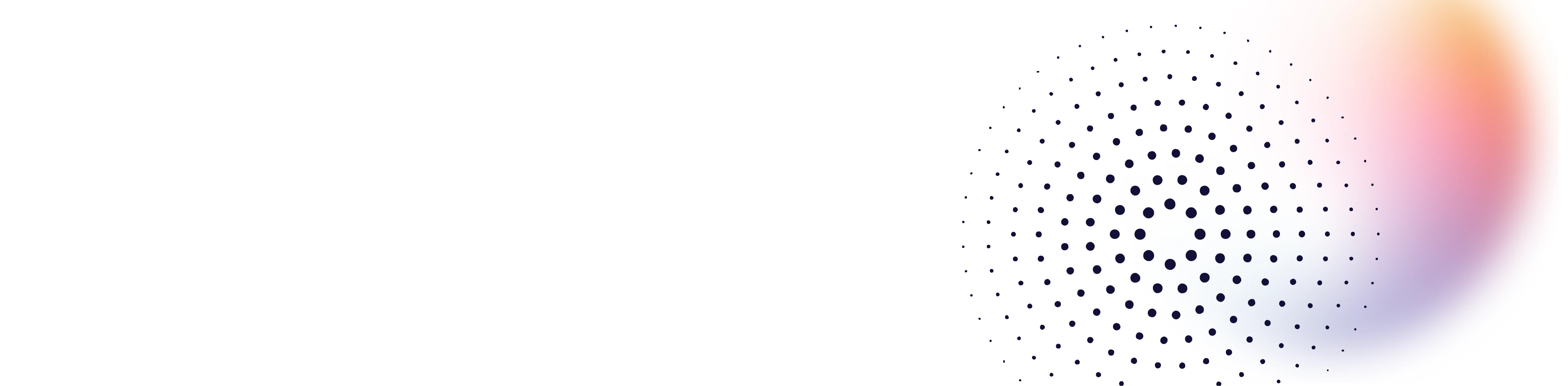2012

健康影響評価に関する専門家会議
2011年の国連総会ハイレベル協議により採択された非感染性疾患(NCDs)の予防および管理に関する政治宣言について加盟国を支持するべく、現存知識の正しい評価と活用に取り組むことを主眼とした「多部門連携による保健事業のためのツールとしての影響評価に関する専門家会議」(2012年6月20日~22日)を神戸にて開催しました。

世界禁煙デー2012記念フォーラム: 「たばこ産業の干渉を阻止しよう」
WHO神戸センターは、2012年5月31日、世界禁煙デーを記念して、公開フォーラム「たばこ産業の干渉を阻止しよう」を神戸にて開催しました。
学界、地方自治体、市民団体等からの60名を超える参加者とともに、日本におけるたばこ政策にみられるたばこ産業の干渉について、見識や意見の交換を行いました。
二時間にわたるフォーラムでは、神奈川県に続き今年兵庫県でも受動喫煙防止条例が採択されるなど、強化されつつあるたばこ規制の取り組みを弱体化させようとするたばこ産業の戦術が浮き彫りにされました。
2004年のたばこ規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組み条約)採択以降、日本は、たばこ市場におけるたばこ産業の業務に関連する法律と、人々の健康を守るためのたばこ規制計画との間で苦労してきました。国立がん研究センター がん対策情報センター たばこ政策研究部長 望月友美子博士は、たばこ規制枠組み条約およびそのガイドラインに基づいた効果的なたばこ規制政策の施策実施における日本の取り組みが不十分であると指摘、その結果として人々の健康が脅かされていることから、命を守るという観点からたばこ規制政策に対する国民意識を高める必要があると論じました。
WHO神戸センター・コンサルタントの柏原美那氏は、日本たばこ産業が意図的に繰り広げる喫煙マナー向上の推進を取り上げ、そのたばこ規制政策への影響について発表しました。たばこ産業の喫煙マナー戦略が、たばこがもたらす健康への影響から人々の注意をそらす目的で使用され、また、たばこ規制政策弱化をねらい地方自治体とのパートナーシップを構築しようとしている現実を紹介しました。
神奈川県は、2009年に屋内の公共の場所での喫煙を制御するための条例を施行した日本初の自治体です。しかし、条例策定の際には、やはりたばこ産業の干渉に苦しめられました。元神奈川県議会議員の関口正俊氏は、実際に展開されたたばこ産業による世論操作について発表。これは、たばこ会社がその従業員に強いて、神奈川県が条例導入に際して実施した世論調査に介入、屋内の公共の場所でのたばこ規制に反対する票を投じさせたというものでした。
プレゼンテーションに続いて、兵庫県医師会副会長 足立光平博士の進行で活発なディスカッションが行われました。ここでは、おもに、神奈川県・兵庫県の両県が体験し、また、日本に広く見られる傾向でもある、たばこ産業のマーケティングとたばこ規制政策実施を妨害する戦略について討議されました。
フォーラムは、WHO神戸センター所長のアレックス・ロスの閉会挨拶をもって終了しました。人々の健康を守るためには、たばこ規制枠組み条約の完全な順守が重要であり、これからも、WHOは、たばこ規制施策強化を通じて健康増進に尽力することを表明して締めくくられました。
関連リンク:
- WHO World No Tobacco Day 2012 website - 英語版
- WHO出版物: Tobacco industry interference with tobacco control(たばこ規制に対するたばこ産業の干渉) - 英語版

パートナーシップを通じた多部門関連携による非感染症予防とコントロール促進のためのインターネット専門家会議の開催
2012年1月の第130回WHO執行委員会で可決された「非感染症予防とコントロール:非感染症予防とコントロールを進める世界的戦略の実行及び活動計画」決議に基づき、WHOでは2012年3月19日から4月19日にかけて、インターネットを介した専門家会議を開催しました。WHO神戸センターでは、専門家会議の基礎文書となる討議資料の提供を行いました。

世界保健デー2012: 高齢化と健康
WHO神戸センターでは、世界の関係機関と緊密に連携し、WHOの「Age-Friendly Cities(高齢者にやさしい都市)」の指標を開発するなど、高齢者にやさしい環境についての研究を行なっています。所在が日本にあることを利用して、日本固有の知見や経験を活用しながら、国内の研究者と協同して、健やかな人生をより長く過ごせるような介入策や政策を特定するための研究を行なっています。
WHO神戸センターは、今年の世界保健デーを記念して、日本における高齢化と健康に関する優先課題について考えるためのフォーラムを地元神戸で開催します。
世界保健デー2012記念フォーラム(4月7日)
『健康な高齢社会を目指して~世界最長寿国日本の軌跡と今後の展望』
テーマ:
- 高齢化と健康に関する国内外の動向
- 今後のビジョンとその実現に向けて必要な取り組み
スピーカー:
(登壇順、敬称略)
アレックス・ロス(WHO神戸センター)
武井貞治(厚生労働省国際課国際協力室)
狩野恵美(WHO神戸センター)
辻哲夫(東京大学高齢社会総合研究機構)
鈴木隆雄(国立長寿医療研究センター)
近藤克則(日本福祉大学健康社会研究センター)
坂東眞理子(昭和女子大学)
モデレーター:
(敬称略)
家森幸男(武庫川女子大学国際健康開発研究所)
世界保健デーは、世界保健機関(WHO)が設立された1948年4月7日を記念して制定されたものです。毎年、各国の指導者から一般の人々にいたるまで、あらゆる人に参加を呼びかけ、世界的に影響を及ぼしている保健課題の1つに焦点をあてたグローバルなキャンペーンが展開されます。そのテーマは年毎に異なります。
"Good health adds life to years"
2012年の世界保健デーのテーマはAgeing and Health(高齢化と健康)であり、"Good health adds life to years" (健康であってこその人生)をスローガンとしています。今年のテーマは、65歳以上の老年人口の割合が世界最大である日本にとって、特に係わりの深いテーマです。生涯、良好な健康状態を保つことで、いかに暮らしが豊かで実り多いものになるか、そして家族やコミュニティにとって必要な人材であり続けられるかといったことに焦点をあてます。
世界の高齢化に関する主要統計
- 現在の世界の60歳以上の人口は、1980年と比べて倍増しています。
- 80歳以上の人口は、2050年までの間に、現在の4倍近い3億9500万人に達すると考えられます。
- 今後5年以内に、65歳以上の人口が、5歳未満の子どもの人口を上回ると考えられます。
- 2050年までには、65歳以上の人口が、14歳未満の子どもの人口を上回ると考えられます。
- 世界の全高齢者の過半数が低所得国または中所得国に暮らしています。この割合は2050年までに80%に達すると考えられます。
人口構成の変化に伴う新たな課題
- 低所得国においても、高齢者の多くは非感染性疾患により亡くなっています。
- 高齢者は慢性疾患のリスクが高まるため、社会の高齢化が進むにつれて、障がいをもつ人の数が増加しています。
- 世界中の高齢者の多くが虐待の危険にさらされています。
- 長期介護のニーズが高まっています。
- 世界的にみて、寿命が延びるにつれて、アルツハイマー病などの認知症患者の数が急激に増加します。
- 災害などの非常時には、高齢者は特に危険にさらされやすくなります。
固定観念の打破
多くの伝統的社会では、高齢者は「長老」として尊敬される存在です。しかし、高齢の男女があまり尊重されていない社会もあります。高齢者の疎外は、公式な制度などによって生じるものから、私的偏見などに起因するものまで様々です。これらを「年齢差別(Ageism)」と呼びます。すなわち、年齢によって、個人やグループに対して固定観念を抱いたり差別したりするということです。これらの固定観念により、高齢者が、社会的・政治的・経済的・文化的・精神的な活動、市民活動などに全面的に関わることが阻まれるという状況が生じています。
主要なキャンペーン・メッセージ
- WHOは、生涯にわたって健康なライフスタイルを維持することにより、より多くの命を救い、健康を守り、特に高齢期における障がいや苦痛を軽減することを奨励します。
- 高齢者にやさしい環境づくり、病気の早期発見と予防および治療を行うことで、高齢者の福祉は改善できます。
- 今すぐに行動を起こさなければ、人口の高齢化は、社会経済発展あるいは人間開発目標の達成を阻害することになります。
- 高齢者は社会にとって価値のある人的資源です。高齢者が、自分は尊重されていると実感できることが必要です。
- 生涯にわたり健康であれば、年を重ねることによってもたらされる恩恵を最大限に享受することができます。
- 高齢者を大切にし、高齢者が積極的に日常生活を送れるような体制を整えた社会は、世の中の変化に上手く適応できるでしょう。
行動宣言
高齢期において良好な健康状態を保つために、次の行動が必要となります。
- 生涯にわたって健康を促進する。
- 高齢者の健康と社会参加を促進するような、高齢者にやさしい環境をつくる。
- プライマリー・ヘルスケア、長期介護や緩和ケアへのアクセスを確保する。
- 高齢者を尊重し、家庭や地域での生活を支援する。
マルチメディア

介護予防の現状と今後の課題
WHO神戸センターは、「介護予防の現状と今後の課題」をテーマに、東京大学及び京都大学からの3人の専門家を招き、2012年3月21日に、神戸市の兵庫女性交流館にてフォーラムを開催しました。本フォーラムには、学術機関、地方自治体及びNGOから60人を超える参加者が集まりました。
2012年のWHO世界保健デー (World Health Day) のテーマは「高齢化と健康」であり、世界最長寿国の日本から健康で豊かな高齢社会を築く秘訣を学ぼうと世界が注目しています。日本においては、2006年の介護保険法改正において介護予防のアプローチが国の制度として導入されて以来、市町村が主体となって様々な介護予防事業やプログラムが実施されています。本フォーラムでは、平成23年度に、WHO神戸センターが、国内の専門家と協力して実施した、介護予防プログラムに関する研究の報告をするとともに、介護予防の今後の課題や展望について討議を行ないました。
基調講演を行なった東京大学大学院医学系研究科教授の甲斐一郎氏は、現在の介護予防プログラムの評価の重要性を述べるとともに、介護予防プログラムが、保健介入であるばかりでなく、福祉介入の側面も持つことを踏まえ、その評価にあたり、保健(健康)指標だけでなく、プログラム受給者の満足度なども評価指標に含めていくべきであることを提言しました。さらに、それらの評価を用いた根拠に基づく介護予防プログラム策定が今後の課題であることを指摘しました。
WHO神戸センターとの共同研究報告では、まず東京大学大学院医学系研究科博士課程の増野華菜子氏が、介護予防プログラムの効果に関する文献レビューの結果を発表し、転倒予防を含む高齢者の身体機能改善に対する効果についての研究発表は多くなされているが、その他の口腔衛生、栄養、認知症、精神保健などに対する効果についての検討が乏しく、今後の課題であることを紹介しました。さらに、京都大学大学院医学研究科博士課程の木村友美氏は、介護予防の効果的に運用するためには、体系的な評価を実施することが重要であることを前提としたうえで、具体的な評価手法について実例を交えながら紹介し、さらに評価指標の一つとして定着しつつある「健康寿命」について、その有用性と限界などについて詳しく説明しました。
発表後は活発な質疑応答が行われました。介護予防プログラム研究者とプログラム施行者の間の様々なギャップ改善のためのアプローチの1つとして、研究者による積極的な介護予防に関わる地方自治体職員の育成への貢献と実務者側の的確なニーズ把握が有効なのではないかとの意見が出されました。また、高齢者の健康問題には性別による違いがあることから、性別に基づいた特有の介護予防プログラム提供についても、今後の検討課題のひとつとして議論が交わされました。
「第15回 たばこか健康か世界会議」にて、ワークショップを開催
シンガポール -- WHO神戸センターは、 シンガポールで開催された第15回 たばこか健康か世界会議(2012年3月20日~24日)会期中の3月20日、プレカンファレンス・ワークショップ「禁煙都市を目指して: 効果的な禁煙法のための12ステップ」を主催しました。本ワークショップは、自治体レベルの政策立案者やたばこ規制推進者を対象にしたもので、WHO神戸センターがWHO本部のたばこ規制担当部局とともに開発した禁煙都市を目指すための手引きが紹介されました。

2011年東日本大震災から1年を迎えて
2011年3月11日の大震災は、災害への備えと発災後に求められる災害対策協調の必要性、ならびに長期的な復興支援の重要性を明らかにしました。この分野において、WHOは行政府や自治体に対し戦略的なガイダンスを提供するなど、重要な役割を担っています。
WHOは、西太平洋地域事務局・神戸センター・本部の協調体制のもと、被災地域ならびに、国や自治体への支援を行っています。しかしながら、いかなる災害時でも、真っ先に対策を迫られるのは被災地自体です。東日本大震災から得られた日本の災害対策の実態や経験は、世界の他の地域が災害対策に取り組むにあたり、大きく貢献することでしょう。
近隣の市町村が甚大な被害を被る中、遠野市では、幸い死亡者はなく、家屋の倒壊等の被害もありませんでした。WHO神戸センターでは、2011年11月、遠野市の本田敏秋市長をお迎えし、市の防災戦略についてご発表いただきました(写真)。遠野市は、大震災の発災直後に後方支援活動本部を設置、速やかに必要な救援物資を被災地へ届けるなど、多くのボランティアを組織的に動員し、有益な後方支援活動を遂行しました。
関連リンク
2011
市民社会の働きかけが禁煙法執行を促進
世界禁煙デーシリーズPart 8:インド・チャンディーガル 2003年制定のインドたばこ規制法の実施強化は地方自治体の責任であるのもかかわらず、チャンディーガル市では法律施行の努力をほとんどしていませんでした。2007年、情報開示法 (2005年制定)をうまく使い、市民団体が市に公的機関のたばこ 規制法に順守状況を開示するよう嘆願を提出しました。 必須とされている禁煙サインを掲示している公的機関 や喫煙所の数、その他の規定の実施状況の報告 を含む嘆願に対応せずに情報開示法違反の罰金が課せられるのを恐れた市政府は、禁煙サインを表示したばこ規制強化を実施しました。これにより たばこ規制法の存在が知られるようになり、公的機関、民間機関に対し法の順守を更に強化するためのNGOと市政府のパートナーシップへと発展しました。
絵や写真での警告表示がたばこ製品の包装で増加傾向に
現在、たばこ製品の包装に大きな写真や絵で健康に関する警告表示を義務づける法律のある19カ国に、合わせて10億以上の人が住んでいます。この数は2年前に比べ、倍近くに増えました。本日発表されたWHOの報告書:Report on the global tobacco epidemic 2011には世界のたばこ規制措置の進捗状況がまとめられています。大きな写真・絵による健康に関する警告は、WHOの推奨する6つのたばこの需要減少措置の一つです。

ポリオ撲滅に向けて最後の一押し
「ポリオをなくそうチャリティーコンサート」が国際ロータリー第2680地区主催で、兵庫県公館で催されました。ポリオは主に5歳以下の小児が感染し、少数の感染者(約0.5%)には一生続く麻痺が残り、場合によっては死に至る疾病ですが、ワクチンで予防可能です。1988年、166カ国の代表が出席した第41回世界保健総会においてポリオを世界から撲滅する決議を採択し、これにより「ポリオ撲滅のためのグローバルイニシアティブ」”Global Polio Eradication Initiative” が WHO、国際ロータリー、米国疾病予防管理センター(USCDC)とUNICEFにより推し進められてきました。これまでの成果は絶大で、現在ポリオ常在国はアフガニスタン、インド、ナイジェリア、パキスタンの4カ国のみとなっています。
この長年のグローバルなパートナーシップに基づき、コンサートにはWHO神戸センターのクマレサン所長が招かれ、井戸敏三兵庫県知事とともに開会のあいさつに立ちました。続いて行われたパネルディスカッションでは、元WHO本部のメディカルオフィサーで現在は国立感染症研究所でポリオ等感染症対策を担当なさっている中島一敏氏が世界のポリオについて、丸山小児科医院院長の丸山義一氏が日本で見られたポリオについて、兵庫県立こども病院院長の丸尾猛氏が日本でのポリオワクチンに対する最近の論点などについてお話されました。進行役は神戸大学の中園直樹教授が務められ、専門的な内容を分かりやすくご紹介くださいました。 会場は満員で、立ち見もでる盛況ぶりでした。