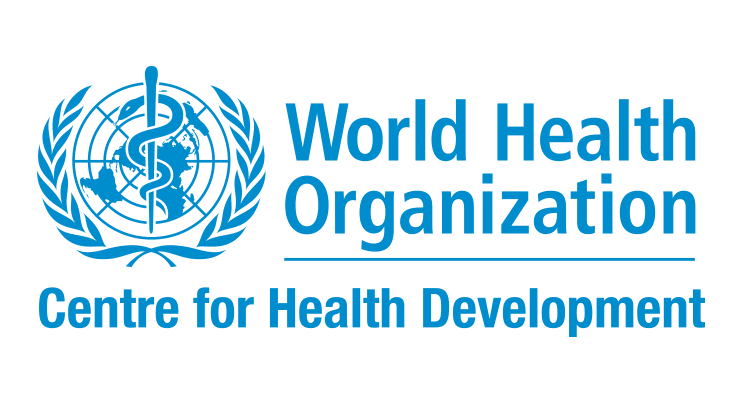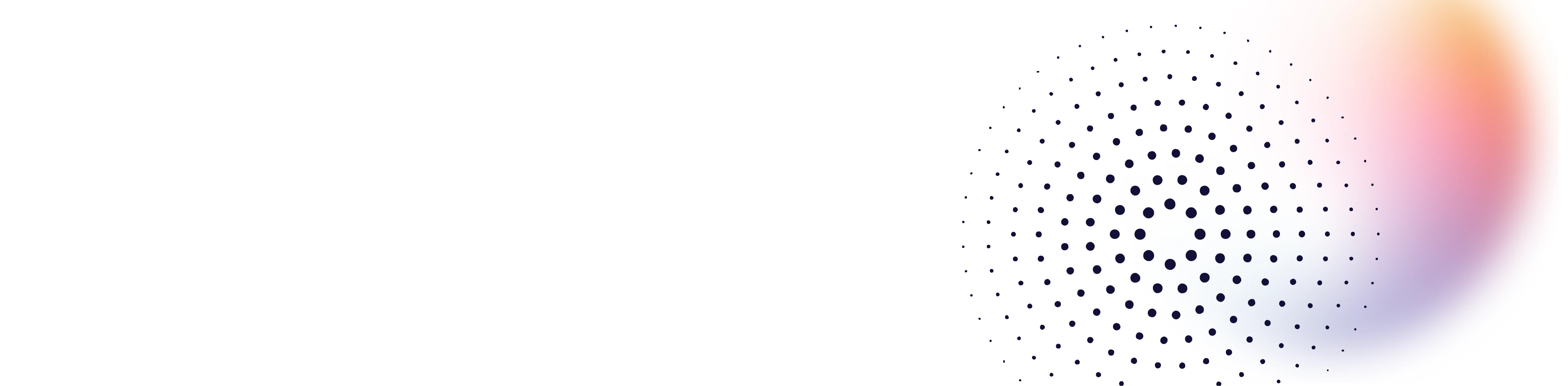2014

都市部における健康の公平性評価・対応ツール(アーバンハート)の改訂
世界の都市人口は2000年に比べ10億人以上増加しています。この増加のうちの9割は開発途上国で進行しました。2050年までには約64億人が都市部に居住し、そのうち約20億人がスラムに居住すると予測されています。都市部では、富や健康、資源へのアクセスにおける不公平が引き続き重要課題となります。
今日までWHO神戸センターは、『都市部における健康の公平性評価・対応ツール(アーバンハート)』の実用化のために世界40カ国の都市と協力してきました。またアーバンハートの実用化事例の記録も進め、2014年にはそれらをもとにした二つの論文を発表しました。
現在、WHO神戸センターはアーバンハートを実施した各都市のフィードバック、専門家からの提言および第三者評価をもとにしたアーバンハートの改訂に取り組んでいます。そのために、WHO神戸センターは、これまで何らかの形でアーバンハートを使用したことのある人や団体からの意見や提言を募っています。

WKCフォーラム「高齢者のためのイノベーション ~アドヒアランス向上のために: 薬剤治療と食事療法~ 」
10月1日は、国連の定める 国際高齢者デー(International Day of Older Persons)です。この日を記念して、WHO神戸センター(WKC)は、2014年10月1日(水) 神戸にて、公開フォーラム「高齢者のためのイノベーション ~アドヒアランス向上のために: 薬剤治療と食事療法~」を開催します。
人口に占める高齢者の割合は、世界的に急激な増加の一途をたどっています。現在、ほとんどの国で、最も急速な増加がみられる人口区分は80歳以上の高齢者層です。今後40年のうちに、高齢者人口は現状のほぼ3倍に拡大すると予測されており、この現象の大部分は開発途上国に集中するとみられています。このような人口転換に伴って疾病構造の変化(疫学的転換)もみとめられています。世界的にみて、非感染性疾患が主な死亡原因となり、また、非感染性疾患に起因する障害の割合は障害全体の50%にも上っています。この傾向がきわめて顕著な日本は、世界で最も高齢化の進んだ国であると同時に、非感染性疾患が死亡原因の80%近くを占める現状を抱えています。
従来、医療における患者の療養行動は、「医療者からの指示に患者がどの程度忠実に従うか」というコンプライアンス概念のもと、受身の立場で評価されてきました。しかし、治療の過程では、服薬、食生活の改善、生活習慣の修正など、患者と医療者が相互に合意した治療方針に患者自身が主体的に参加する必要性が重視されるようになってきました。この概念をアドヒアランスと呼びます。
加齢に伴う健康課題の多くについては予防や管理が可能です。そのためには、老化による認知や機能の低下、また、健康や生活の質の維持を目的とした療法にいくつも取り組まなければならないなど、高齢者が日々直面する問題にうまく対処することが肝要です。アドヒアランスは、治療を成功に導く第一の決定要因です。アドヒアランスが不十分であれば、治療効果を最大限に引き出すことは難しく、ひいては、医療制度における全般的な有効性を引き下げることにもつながります。
加齢とともに、栄養必要量は変化していきます。同時に、健康問題や複数の薬剤服用による副作用、生活様式の変化、知識不足などが原因で、必要な栄養摂取が損なわれることも考えられます。食習慣や服薬におけるアドヒアランスは、健康な高齢化のための大切なポイントとして、健康状態の改善に深く結びつています。
今回のフォーラムでは、老年学、薬学、栄養学の分野から4 名の専門家を迎え、高齢者の健康に寄与するアドヒアランス向上についての講演、ならびに、参加者からの質疑に応じる形式での活発な討議を展開します。
開催日時・場所:
2014年10月1日(水)14:00~16:00
WHO神戸センター
プログラム:
(言語:日本語)
14:00~14:05 開会の辞
14:05~15:20 講演
15:20~15:55 討議(オープンディスカッション)
15:55~16:00 閉会の辞
講演者: (登壇順・敬称略)

「服薬と栄養についてのアドヒアランス: 健康で幸せな高齢期のために」
神戸大学 小田利勝 名誉教授
北海道大学文学部、同大学院文学研究科で社会学を専攻。北海道大学助手、徳島大学助教授、教授を経て1996 年神戸大学教授、2007 年神戸大学大学院教授、2013 年3 月定年退職。学術博士(1987 年、北海道大学)。保健医療行動や病気を抱えた家族の生活過程、地域の保健医療システム、個人や組織の国内外での災害対応行動、マレーシアの農村開発、高齢者問題や少子・高齢化問題など、人間と社会をめぐる種々の問題に関して社会学や社会心理学、地域計画学の観点から幅広く研究してきた。近年では、主にサクセスフル・エイジングの研究を進めており、現在は、少子高齢・人口減少社会におけるサクセスフル・エイジングの実現には老年学的想像力の発揮が必要であるという認識に基づいて研究を進めている。
『かつて高齢者は、「役割なき役割」の中に閉じ込められていて、果たすべき重要な役割を持たない、と言われたことがあります。しかし、少子・高齢化が進行する日本において、今日およびこれからの高齢者には多大な役割を果たすことが期待されています。それらの役割の中には、労働力として、また消費人口として経済を支える役割や一大勢力を形成するようになった有権者として政治に果たす役割、そして、何よりもできる限り長期にわたって自立生活が可能なように健康を維持する役割が期待されています。栄養摂取や服薬は、そのための基本的手段ですが、服薬が必要になったときには、病人に期待される役割が生じます。アドヒアランスとは、社会学的に言えば、期待される病人の役割を遂行することです。講演では、幸せな高齢期の生活すなわちサクセスフル・エイジングの実現へ向けたアドヒアランスや栄養摂取について、社会学や老年学の理論から話題を提供します。』

「高齢者の服薬をモニタリングする新たなツール: 日本における臨床研究」
横浜薬科大学 臨床薬学科 薬理学研究室 定本清美 教授
東邦大学医学部卒。リウマチ学を専攻、医学博士(東邦大学)。専門は、内科リウマチ・膠原病学、臨床薬学。東邦大学、東海大学にて臨床リウマチ学を研究。英国・バーミンガム大学では社会科学修士を取得、リサーチフェローとして関節リウマチの臨床にも従事。英国より帰国の後、東邦大学医学部にて病院管理にも携わる。薬学分野では、東邦大学での研究・教育活動の後、2013年より横浜薬科大学にて現職。東邦大学在籍時に着手した患者の服薬を容易にするためのユニバーサルデザイン包装などの臨床薬学における研究は、関節リウマチ患者や障害者、高齢者の負担軽減にも関連づけた成果が期待されている。
『医療においては様々な治療が施行されますが、薬物治療はどんな場合でも根幹となる重要なものです。薬物治療を受ける機会が多い高齢者にとって、薬を正しくまた無駄なく服用することは、個人の治療効果の向上に必要なばかりでなく、医療経済的な意味においても重要であるといえます。共同開発した服薬をモニタリングするツールを用いて、服薬についての臨床研究を行った背景や結果、今後の展開の可能性などについて述べたいと思います。』

「日本人高齢者の栄養と健康維持」
名古屋学芸大学大学院 栄養科学研究科 下方浩史 教授
1977年名古屋大学医学部卒。1982年名古屋大学大学院博士課程満了(第3内科)。名古屋大学医学部老年科に医員として入局。1986年~1990年米国国立老化研究所(NIA)へ客員研究員として留学。1990年広島大学助教授、1996年国立長寿医療センター研究所疫学研究部長、2010年予防開発部長を経て、2013年より現職。2014年からは名古屋学芸大学健康・栄養研究所所長を兼務。厚生労働省の長寿科学総合研究、認知症対策総合研究などの主任研究者として長寿、老化に関する疫学的研究を行っており、栄養や運動などの生活習慣が老化や老年病に及ぼす影響を解明して、健康長寿を達成するための方法論の確立を目指している。
『健康長寿を目指すには食生活の改善が有用です。現代社会ではメタボリックシンドロームと老年病が大きな問題になっています。肥満は多くの疾病の原因ではありますが、75歳以上の後期高齢者ではむしろ栄養不足への対策が重要です。栄養は高齢者の健康維持の鍵となっています。しかし、食生活と疾病との関係には個人差が強く現れます。今後は個人差に注目した疾病予防が重要な時代となるでしょう。』

「高齢期に適切な食事摂取とは」
京都大学東南アジア研究所 日本学術振興会特別研究員 木村友美
2007年奈良女子大学食物栄養学科卒。2009年京都大学医学研究科社会健康医学系専攻専門職学位過程修了、2012年同専攻博士課程修了、博士号(社会健康医学)取得。2011年より、WHO神戸センターの研究プロジェクトに参加し、「都市化と健康」に関するデータベースの構築、日本の介護予防事業や健康寿命についての研究に携わった。2014年より、日本学術振興会の特別研究員として京都大学東南アジア研究所に勤務。地域に暮らす高齢者の健康状態や食事摂取状況を包括的にとらえる「フィールド医学」調査を行っている。高齢者の健康と食に関する科学的エビデンスを蓄積し、「食からの介護予防」を目指している。
『「バラエティ豊かな食事を」とは、厚生労働省の提示する食事指針にも記されている標語ですが、多様な食品の摂取が健康長寿に寄与することは、実際に世界の様々な研究で報告されています。しかしながら、加齢とともに、食の多様性は乏しくなると言われており、その要因は、加齢に伴う運動量の低下、消化機能や咀嚼能力の低下など、複合的で多岐にわたります。また、高齢になると、様々な慢性疾患を複数かかえているという人が珍しくないため、そのような疾患に配慮した食事摂取も必要になってきます。食は単に栄養素の摂取だけでなく、日常のなかでの楽しみや人との交流に関わる重要な側面をもち、心理的な健康度に関与します。高齢者の虚弱を防ぎ、心身ともに健康な状態を維持するための食事摂取について、これまでのフィールド調査や世界の研究報告から考察します。』
詳しくはこちら:フォーラム開催のご案内・参加申し込み方法
参加費無料
事前申し込み締め切り:
2014年9月26日 (金)

IFA第12回高齢化に関する世界会議 2014年6月10日~13日 インド・ハイデラバード
2014年6月10日~13日、インド・ハイデラバードにて、世界高齢者団体連盟(IFA) が「健康・保障・コミュニティー」をテーマに、第12回目を数える世界会議を開催しました。
49カ国から300名余りが参加した会議では、高齢者の権利、非感染性疾患、加齢に伴う障害、介護の質とその基準、所得保障、労働参加、高齢者にやさしい都市・コミュニティー、介護におけるイノベーションなど、関連する議題についての討議、ならびに、取り組むべき課題に対しての提言が行われました。
会期中の6月12日、WHO神戸センターは、「高齢者のためのイノベーション推進:アジア8カ国ににおける高齢者のための医療・補助機器のニーズに関するWHO委託研究の結果から」と題し、シンポジウムを主催しました。

WKCフォーラムレポート「高齢者のためのイノベーション ~加齢に伴う虚弱や障害に対処するために~」
WHO神戸センター(WKC)は、2014年6月24日 神戸にて、公開フォーラム「高齢者のためのイノベーション ~加齢に伴う虚弱や障害に対処するために~」を開催しました。今回のフォーラムには、医療従事者、産業界、研究・学術界、地方自治体などから76名が参加しました。
WHO 本部 障害とリハビリテーション のテクニカルオフィサーを務めるチャパル・カスナビスは、「高齢者のためのイノベーティブな福祉機器 ~加齢による虚弱や障害に対処するために: 概要」について発表し、年齢への配慮ができる知識豊かなサービス提供者の必要性に言及するとともに、アシスティブ・ヘルス・プロダクツ(健康を支える福祉用具・生活支援用具)は、1) コミュニティーに身近かで利用しやすく、2) 費用を誰が負担するかにかかわらず、手頃な価格で入手可能、かつ、究極的には長寿で健康な実りある生活に寄与すべきであると述べました。高齢者が直面する課題に対処するためには、誰もがアクセス可能な医療・技術・社会的イノベーションの融和による総合的な解決策が求められているとして講演を締めくくりました。
 国際義肢装具協会(ISPO)日本支部 会長 陳隆明先生は、「高齢下肢切断者の義足歩行」について講演、近年、世界的に増加している高齢者人口における下肢切断の原因が、動脈硬化や糖尿病による末梢循環障害によって二次的に起こる重症下肢虚血によるものであると発表しました。陳先生は、兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所所長、兵庫県立リハビリテーション中央病院 ロボットリハビリテーションセンター長も務めらておられます。日本では、現在年間4000人のペースで高齢下肢大切断の症例が報告されている現状から、今後の課題として下肢大切断における膝温存率の向上、ならびに、大切断後のリハビリ成功率向上の必要性に言及。また、高齢下肢切断者が義足で歩くために必要な事項として、以下の4点をあげました:1) 歩きたいという強い意志、2) 義足を自己装着できること、すなわち、十分な上肢機能があること、3) 立位を保持できること、4) ある程度歩行できる体力があること。
国際義肢装具協会(ISPO)日本支部 会長 陳隆明先生は、「高齢下肢切断者の義足歩行」について講演、近年、世界的に増加している高齢者人口における下肢切断の原因が、動脈硬化や糖尿病による末梢循環障害によって二次的に起こる重症下肢虚血によるものであると発表しました。陳先生は、兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所所長、兵庫県立リハビリテーション中央病院 ロボットリハビリテーションセンター長も務めらておられます。日本では、現在年間4000人のペースで高齢下肢大切断の症例が報告されている現状から、今後の課題として下肢大切断における膝温存率の向上、ならびに、大切断後のリハビリ成功率向上の必要性に言及。また、高齢下肢切断者が義足で歩くために必要な事項として、以下の4点をあげました:1) 歩きたいという強い意志、2) 義足を自己装着できること、すなわち、十分な上肢機能があること、3) 立位を保持できること、4) ある程度歩行できる体力があること。「切断者こそわが師、地域が教科書」と感慨深く語った 兵庫県立リハビリテーシヨン中央病院 名誉院長 澤村 誠志先生は、「日本の義肢装具教育の沿革: 地域社会に根ざしたリハビリテーション実践の経験から」と題して講演。50年前の日本には、義肢装具に関する教育や義肢装具サービスの向上に関する医学的な組織的活動は皆無であったことを報告しました。事実、当時は義肢装具にかかわる部局を有する医療機関はほとんど存在しませんでしが、兵庫県では身体障害者のための巡回移動相談を実施、リハビリテーションサービスの提供に努めました。巡回のための自宅訪問を重ねる中から、欧米流の義肢装具の手技は、履物を脱ぐ、畳に座るなどといった日本独特の生活様式には適さないことが判明、地域に根ざしたリハビリテーション(CBR)という概念が生まれました。1968年神戸において澤村先生の主導により義肢装具研究同好会が発足、以来、関連する医療従事者のための資格研修プログラムの開発など、学術的、また制度上の動きが自治体、国、そして国際レベルで展開されました。澤村先生は発表のまとめにあたり、いかなる理由によっても誰も排除されることなく、コミュニティー全体が互いに協力して発展を目指す、「地域に根ざしたインクルーシブ(包括的)な開発 (CBID)」こそが肝要であると述べました。
 熊本総合医療リハビリテーション学院 義肢装具学科 学科長 小峯敏文先生は、義肢の採寸から適合までを担う「人と機械を融合する専門職」としての義肢装具士について、その基本的な役割を説明、「日本の義肢装具教育: 福祉用具学導入とその背景」について発表しました。義肢装具士養成の課程は、医学・工学・社会学などの諸領域における多角的な視野を備えながら義肢装具学を修めることを旨とします。2014年4月現在、日本における義肢装具士国家試験の合格者数は4470名。身体に障害を抱えて暮らす人々の数が増加の一途をたどる現状(2012年には約390万人)から、また、65歳以上がその63%を占めるという実情から、今後はさらに、高齢者のニーズに即し、車いすなどの福祉機器の適切な活用と適合(車いすの場合は、使用者の座位をきちんと適合させるなど)の向上が継続的に必要であると述べました。
熊本総合医療リハビリテーション学院 義肢装具学科 学科長 小峯敏文先生は、義肢の採寸から適合までを担う「人と機械を融合する専門職」としての義肢装具士について、その基本的な役割を説明、「日本の義肢装具教育: 福祉用具学導入とその背景」について発表しました。義肢装具士養成の課程は、医学・工学・社会学などの諸領域における多角的な視野を備えながら義肢装具学を修めることを旨とします。2014年4月現在、日本における義肢装具士国家試験の合格者数は4470名。身体に障害を抱えて暮らす人々の数が増加の一途をたどる現状(2012年には約390万人)から、また、65歳以上がその63%を占めるという実情から、今後はさらに、高齢者のニーズに即し、車いすなどの福祉機器の適切な活用と適合(車いすの場合は、使用者の座位をきちんと適合させるなど)の向上が継続的に必要であると述べました。講演に続いて行われたオープン・ディスカッションでは、陳先生がモデレーターを務め、包括的な開発、チームアプローチ、健康保険、保健・医療に関する研究など、具体的な項目について討議が行われました。パネリストからは、以下の点についての認識と周知が必要であるとの指摘がありました:1) CBIDに関する事例やモデル(例: 福島におけるプロジェクト)、2) 年齢に配慮のある学際的なチームアプローチの運用(例: 義肢装具士、作業療法士、理学療法士の協働)により、老若の別によらずどの患者にとっても確かな効果をもたらす取り組み、3) 福祉用具・生活支援用具を国の健康保険・保障制度の枠に含める保健システム(例: フィリピンにおける現行のイニシアチブや2000年に施行された日本の介護保険)、4) 使用者としての高齢者自身の意向や好み、また、福祉用具・生活支援用具の恩恵を取り込んだ、実証に基づいた研究、遡及的かつ先見的な研究。
フォーラムの閉会にあたっては、WHO神戸センター協力委員会の支援、ならびに、ISPO日本支部、兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所両機関からの協力に対し謝意が述べられました。

プログラム・講演者
プレゼンテーション
- 「高齢者のためのイノベーティブな福祉機器 ~加齢による虚弱や障害に対処するために: 概要」
世界保健機関(WHO) 本部 暴力・傷害の防止と障害部局 障害とリハビリテーション
テクニカルオフィサー チャパル・カスナビス
- 「高齢下肢切断者の義足歩行」
国際義肢装具協会 (ISPO) 日本支部 会長 兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所 所長
兵庫県立リハビリテーション中央病院 ロボットリハビリテーションセンター長 陳 隆明
- 「日本の義肢装具教育の沿革: 地域社会に根ざしたリハビリテーション実践の経験から」
兵庫県立リハビリテーシヨン中央病院 澤村 誠志 名誉院長
- 「日本の義肢装具教育:福祉用具学導入とその背景」
熊本総合医療リハビリテーション学院 義肢装具学科 小峯 敏文 学科長

第7回世界都市フォーラム(The 7th Session of the World Urban Forum – WUF)
WHO神戸センターは、コロンビアのメデジン市にて、2014年4月4日から11日に開催された、第7回世界都市フォーラム(The 7th Session of the World Urban Forum – WUF)において、以下の2つのトピックについてネットワーキングイベントを主催しました。
1. ポスト2015年開発アジェンダにおける健康の公平性と持続可能な都市開発― 世界保健機関(WHO)・国際連合人間居住計画(UNハビタット)共同レポート 第2版
2. 健康と公平性に配慮した多部門連携による都市計画
また、WHO神戸センターは、展示ブースにてセンターの活動について紹介しました。
世界都市フォーラムは、UNハビタットの主催で2年毎に開催される国際フォーラムで、急速な都市化が都市やコミュニティー、経済、気候変動、政策などに与える影響をはじめとする、人間居住に関する差し迫った国際課題について議論がされます。WHO神戸センターは2010年よりUNハビタットと協同し、都市問題についての共通課題に取り組んでいます。

世界禁煙デー2014:たばこ税の引き上げを
毎年、世界では600万人近くのい人々が喫煙の流行により死亡していますが、そのうち60万人以上が非喫煙者で受動喫煙によって死亡しています。我々が行動を起こさない限り、喫煙の流行により2030年までには年間800万人以上が死亡すると推計されます。この予防可能な死のうち、80%が低・中所得国で起こっています。
2014年度世界禁煙デーでは、WHOはパートナーと共に、各国政府に対してたばこ税の引き上げを呼びかけます。
たばこ消費量を減らし、命を救う
WHOたばこ規制枠組条約(Framework Convention on Tobacco Control;FCTC)の規定に基づき、各国政府はたばこ消費量を減らす方法としてたばこ製品に対する課税処置と価格設定政策を実行しなければなりません。たばこ税が高ければ高いほど、特に低所得国の喫煙者を効果的に減らすことができ、かつ若年層の喫煙開始を予防することができるとの研究結果が出ています。たばこ製品の価格を10%引き上げるための課税処置によって、高所得国では約4%、低・中所得国では約8%のたばこ製品消費量を減らすことができます。
さらに、たばこ製品への消費税を上げることは、たばこ規制を勧める上でもっとも費用対効果が期待できる方法と考えられます。2010年世界保健報告書では、たばこ製品への消費税を50%上げることによって、低所得国22カ国において14億米ドル強の追加資金を調達できることが報告されています。
キャンペーンの目的
世界禁煙デーの最終的な目的は、たばこによる計り知れない健康被害だけではなく、たばこの消費及び受動喫煙が健康、社会、環境、経済に及ぼす破壊的な影響から、現在及び将来の世代を保護することに貢献することです。
2014年の世界禁煙デー・キャンペーンでは特に以下の目的に焦点を当てています。
- 政府当局が、たばこの消費量を減少させるに十分なレベルまでたばこ税を引き上げること。
- 個々人や市民団体に対し、自国政府当局に対してたばこの消費量を減少させるに十分なレベルまでたばこ税を引き上げるように働きかけることを支援すること。
WHOおよびそのパートナーは、毎年5月31日を世界禁煙デーと定め、世界各地において、たばこがもたらす健康リスクを強調するとともに、たばこの消費削減に向けた効果的な政策への提言を行っています。たばこの消費は世界的に見ても、予防可能な唯一最大の死亡原因であり、現在世界の成人死亡原因の10%以上の原因となっています。

WKCフォーラム「高齢者のためのイノベーション ~加齢に伴う虚弱や障害に対処するために~」
WHO神戸センター(WKC)は、2014年6月24日(火) 神戸で公開フォーラム「高齢者のためのイノベーション ~加齢に伴う虚弱や障害に対処するために~」を開催します。
2020年までに、世界の人口は77億人に達する と予測されています。このうち、65歳以上の人口は10億人に上る一方で、5歳未満の子供の人口は6億5千万人にとどまる見込みです。すなわち、世界の人口統計は、今、確実かつ急速な高齢化というこれまでにない変化を示してます。
今回のWKCフォーラムは、神戸市・三田市を会場に近く開催される「世界義肢装具教育者会議」(ISPO GEM: 6月25日~27日)を機に、国際義肢装具協会日本支部(ISPO Japan)、ならびに、兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所の協力の下、超高齢化社会を迎える日本社会において、加齢がもたらす身体機能の衰えや障害といった課題に焦点を当て、福祉機器におけるイノベーションを手段とした対処策をテーマに取り上げます。
本フォーラムでは、WHOの専門官が日本の専門家3名とともに、それぞれの分野から実証に基づいた研究成果や現状について発表します。また、高齢者が現在抱えている、あるいは、これから直面する可能性のある虚弱や障害といった課題に向けていかに取り組むべきか、イノベーティブな福祉機器を用いての対処策を報告、提案します。さらには、健康な高齢化のためのイノベーションの向上を目指して、障害・福祉機器・地域社会に根ざしたリハビリテーション・義肢装具教育など、多様な研究や診療の経験を有する専門家が、参加者からの質疑に応じる形式で活発な討議を展開します。
開催日時・場所:
2014年6月24日(火)14:00~16:00
WHO神戸センター
プログラム:
(言語: 日本語)
14:00–14:10 開会の辞
14:10–15:20 講演
15:20–15:55 討議(オープンディスカッション)
15:55–16:00 閉会の辞
講演者:
(登壇順・敬称略)
「高齢者のためのイノベーティブな福祉機器~加齢による虚弱や障害に対処するために:概要」
世界保健機関 (WHO) 本部 暴力・傷害の防止と障害部局 障害とリハビリテーション
テクニカルオフィサー チャパル・カスナビス
1979年、インド・ムンバイのAll India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation の義肢装具エンジニアリング学部を卒業。リハビリテーション科学修士(英国・ストラックライド大学)。14年間のインド社会福祉省勤務の後1994年の退職を機にNGOモビリティ・インディア(Mobility India) を設立、9年間にわたりその活動を主導。その後、WHOに移り現職、地域社会に根ざしたリハビリテーション(Community-based Rehabilitation – CBR)と福祉機器の普及に取り組む一方でCBRガイドライン作成に尽力している。
『人は誰しも、加齢に伴う機能低下を避けて通ることはできません。しかし、老化がもたらす虚弱や障害、そして孤独感といった課題は、歩行器や車椅子、人口装具、補聴器や低視力者用補助具、また、日常生活動作を補助する機器やモバイルアプリケーションなどの福祉機器(AT)の活用により、予防、抑制、さらには矯正することが可能です。これまで障害を持つ人達のために開発・改良されてきたATは、高齢化社会を迎えた今、加齢に伴う虚弱や障害といった高齢者のためのニーズに応えることが期待されています。』
「高齢者のための人工装具」
国際義肢装具協会 (ISPO) 日本支部 会長 兵庫県社会福祉事業団 福祉のまちづくり研究所長
兵庫県立リハビリテーション中央病院 ロボットリハビリテーションセンター長 陳 隆明
1986年徳島大学医学部卒。1992年医学博士(神戸大学)。同年より兵庫県立総合リハビリテーションセンターに勤務、2006年から同中央病院整形外科部長兼リハビリテーション科部長、2011年からはロボットリハビリテーションセンター長も務める。多くの障害者に大きな恩恵をもたらすロボットテクノロジーのリハビリテーション分野への応用、特に筋電義手の普及に尽力している。2014年4月からは兵庫県立福祉のまちづくり研究所長として、「安全・安心まちづくり、すまいづくり支援等の研究」、「福祉用具やリハビリテーション支援技術等の研究開発」を主導している。
『近年、超高齢化を背景として、動脈硬化や糖尿病といった疾患が下肢切断原因の主なものとなっています。その結果として、下肢切断者に占める高齢者の割合が大きくなっています。義足で歩くことは、成壮年の切断者にとっては大きな困難ではありません。しかし、義足歩行を獲得するためのリハビリ過程は高齢者にとっては大変困難な過程であり、リハビリの成功率も低いのが現実です。専門性の高いスタッフによるチームアプローチが成功のための重要なカギと言えます。高齢者の義足歩行について紹介したいと思います。』
「日本の義肢装具教育の沿革:地域社会に根ざしたリハビリテーション実践の経験から」
兵庫県立リハビリテーシヨン中央病院 名誉院長 澤村 誠志
1955年神戸医大卒、整形外科入局。その後、米国UCLA義肢教育プロジェクトで義肢製作研修を受ける。1969年兵庫県立総合リハビリテーションセンター開設後、副院長、院長、所長職を歴任、2001年より、顧問、名誉院長として現在に至る。専門領域である整形外科、義肢装具、地域リハビリテーションについての著書、講演多数。1995~1998には、国際義肢装具協会(ISPO)会長を務めた。
『父が下腿義足者であり、尚かつ義肢製作者であったことから義足の研究を目指し整形外科の道を選びました。1955年頃の日本には、義肢装具に関する教育は皆無であり、また、関連職種間の連携の場もありませんでした。そこで、1968年日本義肢装具研究同好会が神戸で発足、これが現在の日本義肢装具学会につながっています。1990年に立ち上げた日本リハビリテーション病院施設協会では、障害のある人々や高齢者およびその家族の支援を目指し、地域に根ざしたリハビリテーションを実践しています。』
「日本の義肢装具教育:福祉用具学導入とその背景」
熊本総合医療リハビリテーション学院
義肢装具学科 学科長 小峯 敏文
1982年国立久留米工業高等専門学校卒。1985年国立障害者リハビリテーション学院義肢装具学科卒。1994年佛教大学通信教育部社会福祉学科卒。1985年~1988年には米国・Leimkuehler Inc. にて義肢適合士研修、1988年米国義肢適合士取得、1988年義肢装具士免許取得。義肢装具士教育においては、国立障害者リハビリテーション学院を経て、1994年より熊本総合医療リハビリテーション学院、1996年より現職。
『義肢装具士は関係医療職種に含まれますが、非常にユニークな職種です。疾患や障害を抱えている方々を対象として、義足・義手・装具といった用具を製作し、適切に身体へ適合することを専門としています。高齢化が進む日本では介護保険制度等の方策が取られています。車いすや杖といった福祉用具も多様なものがより広く用いられるようになってきましたが、適切に使用者に適合しているでしょうか。義肢装具士養成においては、義肢装具以外の身体適合を必要とする福祉用具にも焦点を当てた講座を開設しています。講演では幾つかの臨床例を紹介しながら、直面している課題を提起します。』
参加費無料
事前申し込み締め切り:
2014年6月20日(金)
詳しくはこちら:

11回 都市部の健康に関する国際会議: 2014年3月4-7日
WHO事務局長補マリーポール・キーニーは、英国マンチェスターで開催された第11回 都市部の健康に関する国際会議(仮訳)” International Conference on Urban Health (ICUH)“ にて、「都市部は、保健医療および社会福祉サービスへのアクセスを向上し、すべての人にとって、より住みやすい環境を作る機会が集中している場です」と述べました。
2014年3月4日から7日まで、英国マンチェスター大学主催で開催されたこの国際会議には、1000人以上の参加者が集いました。WHO神戸センター(WKC)所長アレックス・ロスは、医療費に係る経済的リスクから人々を守るため、都市部におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を実現する重要性を強調しました。
WKCは3つの本会議セッションに登壇したほか、都市部における健康の公平性評価・対応ツール(Urban HEART)のワークショップ実施や、他6つの分科セッションを含む、様々なイベントの企画・運営あるいは講演等を行いました。WKCのICUHへの参加は、情報の共有や交換、ネットワーク構築の強化をする貴重な機会となりました。

世界保健デー2014:節足動物が媒介する感染症から身を守ろう
世界保健デーは、世界保健機関(WHO)が設立された1948年4月7日を記念して制定されたものです。毎年、世界的に影響を及ぼしている保健課題の1つに焦点をあてたグローバルなキャンペーンが展開されます。そのテーマは年毎に異なります。
2014年の世界保健デーのテーマは節足動物が媒介する感染症です。
世界の総人口の半分以上が、マラリアやデング熱、リーシュマニア症や黄熱病など、節足動物(ベクター)が媒介する感染症に罹患するリスクにさらされています。また、貧困層ほどそのリスクが高くなります。しかしながら、気候変動や国境を越えて急速に増え続ける人の移動や物の流通は、この感染症への罹患リスクがさらに広がっていることを意味しています。2014年度のWHO世界保健デーではベクターと、ベクターがもたらす疾患から自分自身や家族を守るため誰でもできる簡単な予防方法に注目します。
ベクターとは?
ベクターとは、蚊やダニ、ノミ、ハエなどヒトとヒトとの間で、あるいは場所から場所に感染症を伝播する生物です。
キャンペーンのゴール
今年のキャンペーンは、ベクターによってもたらされる脅威、そしてベクターによって媒介される感染症について啓蒙すると共に、家族やコミュニティーにおいて自分自身を守るための行動を起こすことです。
目的
- 流行地域に住む人々が適切な予防手段についての知識を持つ。
- 流行地域への旅行者が適切な予防手段についての知識を持つ。
- ベクターによって媒介される感染症が公衆衛生上の問題となっている国々において、保健当局がより適切な予防手段を講じる。
- ベクターによって媒介される感染症が新たな脅威になりつつある国々においては、保健当局が自国又は周辺国の環境当局やその他の関連当局と連携し、感染症を媒介する節足動物の調査を行い、その拡散を防ぐ為の措置をとる。
公衆衛生の関係諸機関が節足動物が媒介する感染症(ベクター伝播疾病)に取り組むには
効果的で長期的なベクター対策と、ベクター伝播疾病の制圧には、十分な資金のある国家対策プログラム、包括的な国家・地域戦略、そして公衆衛生分野のグローバルコミュニティで活動するパートナー機関との緊密な協力が必須です。プログラムが持続可能であるためには、明確な標準業務手順を提示する技術的ガイドラインが必要であり、効率的な物流管理やモニタリング評価によって適切に管理されなくてはなりません。
ベクターの統合管理
WHOは、ベクターの統合管理が、国の保健医療制度と両立する形でベクター対策を強化できる最善の手法であるとして、これを促進しています。ベクターの統合管理に関する重要な要因は以下の通りです。
- 研究によるエビデンスに基づいた政策決定
- モニタリング評価の適切な手法
- 保健医療部門と他の政府部門や民間セクターとの緊密な協力
- 複数の疾病への対策を同時に行うというアプローチによる、人材および財源の活用の最適化
- 様々な介入策を、多くは組み合わせて、あるいは相乗的に活用
- 政策立案および政策決定を可能な限り下の行政レベルに委ねる
- ベクター対策を促進するための、関係諸機関、組織、市民団体による政策提言および社会的動員
- 公衆衛生の規制や法律に関する枠組み
- 地元コミュニティを活性化し、プログラムを確実に持続可能なものにするための、地域コミュニティと協力
- 状況分析に基づいた、国・地域レベルの能力強化
例えば、マラリアとリンパ系フィラリア症の地理的分布が、アフリカ、アジア、アメリカ大陸の大部分で重複していること、そしてハマダラカ属(Anopheles)の蚊が両方の疾病を媒介するという事実を踏まえて、WHOでは、以下の地域において、ベクターの統合管理を推奨しています。
- マラリアとリンパ系フィラリア症の両方が蔓延する地域
- 2つの疾病のベクターに対して、同一のベクター防除策が効果的である地域
また、WHOは、一部の都市部においてデング熱のベクターであるヤブカ属(Aedes)の蚊に対する防除策と、都市部におけるリンパ系フィラリア症の重要なベクターであるネッタイイエカ(Culex quinquefasciatus)の防除策を、統合することを推奨しています。
WHOによる組織ごとへの働きかけ
政府
- 国家や地域、地方など、全てのレベルで、効果的なベクター防除政策の採択および実施にコミットする
- ベクターの防除を、包括的な疾病対策戦略の中に組み込む
- ベクターの統合管理を通して、リソースや体制を合理化する
- ベクター対策のための手段や方法に関して、規制面や法的な面での管理力を強化する
保健省
- ベクター伝播疾病に関するサーベイランスとモニタリングを強化する
- 複数の疾病に同時にアプローチする。例えば、ベクター伝播疾病をコントロールし予防するための介入策を、他の疾病に関する介入策と統合的に実施する
- 包括的な殺虫剤耐性管理戦略の開発と導入を行う
- 他の政府部門と連携する
環境省
- 灌漑、水力発電ダムの建設、道路建設、森林伐採、住宅開発、工業発展などのあらゆる開発プロジェクトにおいて、媒介生物への影響を考慮する
- 安全な飲み水と衛生設備へのアクセスを改善し、寄生虫である住血吸虫が生息する水に人々が接触する機会を低減する
教育省
- 意識向上や行動変化のキャンペーンを支援する(写真:シャーガス病の原因は寄生虫クルーズトリパノソーマ(T. cruzi)ですが、これを宿し感染を広めるサシガメという昆虫を防ぐための教育的なポスター。ボリビアにて。)
- 学校でカリキュラムを組んで、健康と環境のために、ベクター対策やベクター伝播疾病の予防に焦点をあてつつ、環境衛生やベクター伝播疾病の予防管理に集中するよう、教員に積極的に働きかける。生徒は、互いに教え合い(peer education)、家族や近隣に対して「保健大使」として活動できる
財務省や海外開発に関わる省庁
- ベクター対策を国家的な開発課題として認識する
- ベクター対策のための財源を、疾病対策の予算に組み込む
WHOによる組織ごとへの働きかけ
地方自治体の当局
- 国の媒介生物防除政策を地元レベルの実践的取り組みへと転換するための、重要な橋渡しをする
- コミュニティと緊密な連携を取り活動する
環境団体、地元団体、その他のコミュニティグループ
- 健康の社会的・環境的決定要因にともに取り組むために、政府と強固な協力関係を築く
- 意識向上の活動に注力する
- 公衆衛生の改善と水源の保護を呼びかける
- 植物や廃物の撤去など、ベクター対策のための活動を組織する
- ベクターに関する生物学、生態学、防除方法などに関する短期の実践的な訓練コースを通して、コミュニティメンバー、コミュニティの保健医療従事者、農事作業者の能力向上に努める
民間セクターおよび支援団体
- ドナーおよび民間セクターは、対策プログラムを効率的かつ効果的、そして持続的に支援できるよう、連携を強化して活動に取り組む必要がある
- 殺虫剤、次世代のベクター対策ツール、革新的な医薬品や診断ツールの研究開発のためのインセンティブを提供する
- イニシアチブは、モニタリング評価や報告のための適切なシステムや、課題の迅速な特定と解決のための手順とともに進められなければならない
- シャーガス病や住血吸虫症、リーシュマニア症などの多くの疾病に対して、WHOは、民間セクターによる寄付・助成医薬品を利用した対策プログラムを運営している
家族および家庭
ベクター対策のために、個人が以下の活動をすることで、大きく貢献できます。
- 地元地域や旅行先で、どのようなベクターが疾病を媒介するかの知識を習得する
- 殺虫剤処理済みの蚊帳など、ベクターを防除する上で効果が明らかにされている手段を活用し、旅行中に虫に刺されないよう自分の身を守る
- 地方自治体と協力して、住居内の防虫処理のプログラムなどを活用する
- ベクター伝播疾病のリスク軽減に関するコミュニティベースの保健教育に参加する
- 環境管理のキャンペーンに参加する。例えば、家屋周辺に蚊がはびこる元となる、貯留水を減らすためのキャンペーンなどがある
詳しい情報についてはこちら

アーバンハート専門家会議レポート
WHO神戸センターは過去10年間にわたり、自治体や国の当局者が行う健康格差についての取り組みを支援してきました。また、当センターは都市における健康の公平性評価・対応ツール(アーバンハート)を自治体、国の当局者およびコミュニティーが都市の健康格差を特定し是正するために活用できる使いやすい手引書として2008年から提供しています。
アーバンハートは2013年までに50カ国35都市にて活用されてきました。ユーザーおよび専門家によりツール向上のための実質的なフィードバックが提供され、2013年11月にはWHO神戸センターは兵庫県神戸市にて専門家会議を主催し、参加した当該分野の研究者、政策立案者、国際機関による更なるユーザー支援のための、主要領域におけるガイダンスについての協議・検討が行われました。
専門家らはWHOに対してアーバンハート活用の拡大とツールを都市計画の過程に取り入れるための方法に関する助言をしました。会議報告書にはアーバンハートの改訂に関する協議・検討について詳しく述べられています。