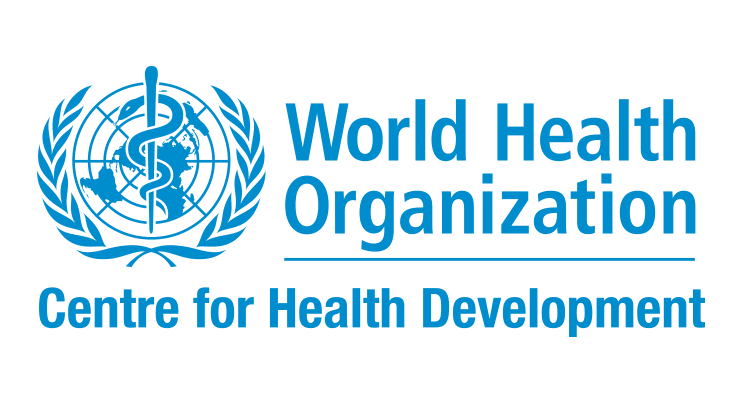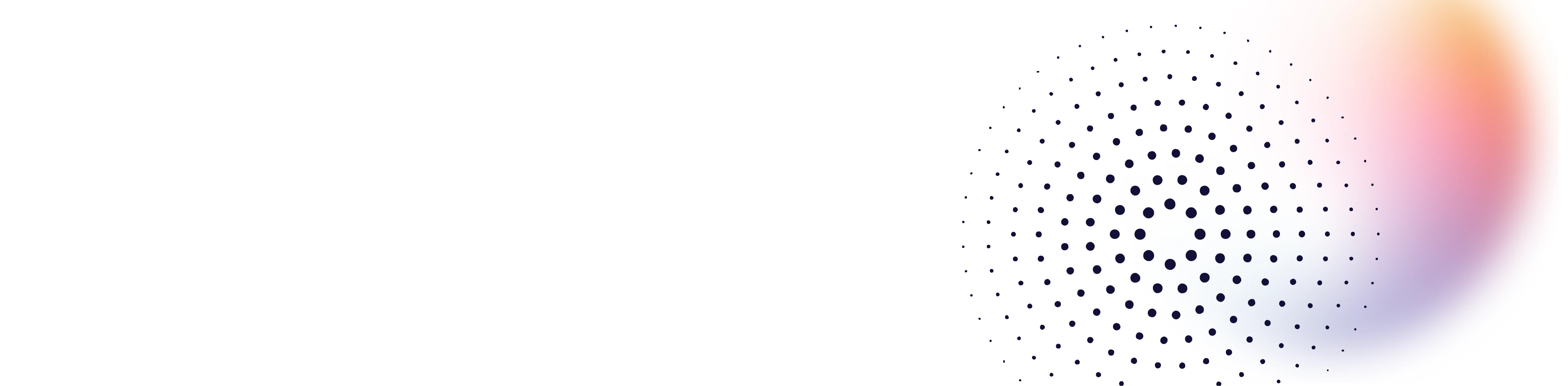WHO神戸センター新研究: 日本の知見を世界に向けて発信

―高齢化とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)に関する研究
高齢先進国の日本には各国に先んじて高齢化対策に取り組み、健康な高齢化を推し進めてきた教訓が豊富に蓄積されています。世界各国が急激な人口動態の変化に対応し保健システムを見直すという大きな課題に直面する中、日本の教訓をもっと生かすことができるのではないでしょうか。
そこで、WHO神戸センターは2017年、日本の研究機関を対象に高齢化が進む世界のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)推進に寄与する日本の知見を研究公募しました。
厳正な審査を行った結果、以下の5つの研究が選ばれ、この度すべての研究が開始する運びとなりました。
WHO神戸センターのサラ・ルイーズ・バーバー所長は「今回の研究の目的は政策・技術面で日本に蓄積されている貴重な教訓を論文化し評価していくことです。世界各国が日本と同じような課題に直面する中で日本の知見が活用されれば嬉しいです」と語っています。
なお、和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 田島 文博 教授と兵庫県立大学 地域ケア開発研究所 広域ケア実践研究部門 山本 あい子 教授は4月7日にWHO神戸センターで開催するWHO神戸センター新研究発表会に参加されます。詳しくは下記のリンクからご覧ください。
WHO神戸センター新研究: 日本の知見を世界に向けて発信
(研究者氏名によるアルファベット順)
日本の長寿者に学ぶ支援機器の利活用
主導研究者: 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 二瓶 美里 講師
研究概要: 支援機器(Assistive products)は高齢者が自宅や地域社会で快適に暮らし、社会の一員として活力のある生活を維持し、さまざまな障害をクリアするために欠かせない存在となっています。そして、高齢者の支援機器利用やサービスに関する経験値が超高齢社会の日本には豊富に蓄積されています。本プロジェクトでは、日本の90歳以上の長寿者が実際にどのような支援機器を使用し、日常生活に活用しているのか実態を調査します。調査結果は国内のみならず世界の福祉・サービス提供における支援機器利用計画に活用されることが期待されます。
高齢者の生活の質を高めるための新しい支援テクノロジーの開発
主導研究者: 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 田島 文博 教授
研究概要: 高齢者にとって身体機能を維持・向上し、日常生活動作(ADL)と生活の質(QOL)を維持することは極めて重要です。本研究は関西地域の5大学による共同プロジェクトで、新しく開発された支援テクノロジーを用いて、a) 入院中の高齢者の機能維持のための活動量評価、b) 転倒リスクの高い姿勢や活動の同定、c) 効果的なリハビリテーション実施のための活動度設定の基礎データ作成を行い、高齢者のADLとQOLの維持・向上のための戦略立案を目指します。
超高齢社会日本のUHC持続に向けた効率的な医療提供とは~大規模ヘルスデータの二次分析~
主導研究者: 産業医科大学 公衆衛生学教室 冨岡 慎一 助教
研究概要: 超高齢社会の日本における一次・二次レベルの医療について、より効率的、公平かつ費用対効果の高い医療を提供するためのエビデンス構築を目指して、 外来、 在宅、 災害時、 急性期病院の4領域に分けた二次分析を実施します。具体的には、DPCデータ、レセプト(診療報酬明細書)データ、J-SPEED(日本版災害時診療概況報告システム)データなどの大規模な二次データの横断的な統計解析を実施することで検討していきます。保健制度・政策の指針となるエビデンスの提供を目指します。
介護分野における外国人技能実習のためのICF(国際生活機能分類)を基盤とした評価ツールの開発
主導研究者: 兵庫県立大学大学院 経営研究科 筒井 孝子 教授
研究概要: 世界で人口高齢化が進行し、現場における介護の負担はますます深刻になっています。この状況は東アジアにおいて顕著で、介護人材の需要は2050年までに少なくとも倍増すると見込まれています。日本では世界的な介護職の人材不足に対応するために「外国人技能実習制度」の対象職種に新たに介護職種が追加されることになりました。これは、介護分野での就労を希望する外国人を対象とした初めての実習プログラムです。本研究ではこの実習プログラムに焦点を当てて、外国人研修者の介護技能習得の達成度を評価するツールの開発を目的としています。また、海外での応用も見据えて、既存の評価ツールの国際生活機能分類(ICF)の活用の可能性も検証します。
災害後の人々の健康維持・回復に向けたケア戦略の開発
主導研究者: 兵庫県立大学 地域ケア開発研究所 広域ケア実践研究部門 山本 あい子 教授
研究概要: 自然災害は大規模化し、かつ頻発に発生しており、災害リスクとその影響の低減の検討が求められ、特に災害弱者の健康への配慮が求められています。本研究は、支援を受けながら生活している高齢者の災害後の基本的なニーズや課題等について明らかにする質的研究と、医療職や行政職を対象とした、PTSD、うつの予防プログラムとその実施における課題を評価する研究とを通じて、よりよい健康危機管理のための提言を目指します。
研究概要一覧
- 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 二瓶 美里 講師
pdf, 575kb - 英語版
pdf, 875kb - 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 田島 文博 教授
pdf, 597kb - 英語版
pdf, 700kb - 産業医科大学 公衆衛生学教室 冨岡 慎一 助教
pdf, 760kb - 英語版
pdf, 837kb - 兵庫県立大学大学院 経営研究科 筒井 孝子 教授
pdf, 880kb - 英語版
pdf, 1.27Mb - 兵庫県立大学 地域ケア開発研究所 広域ケア実践研究部門 山本 あい子 教授
pdf, 734kb - 英語版
pdf, 829kb -
Call for proposals (2017年)
“WHO/WKC Launches New Research Initiative for UHC and Ageing Populations: Lessons from Japan” - 英語版